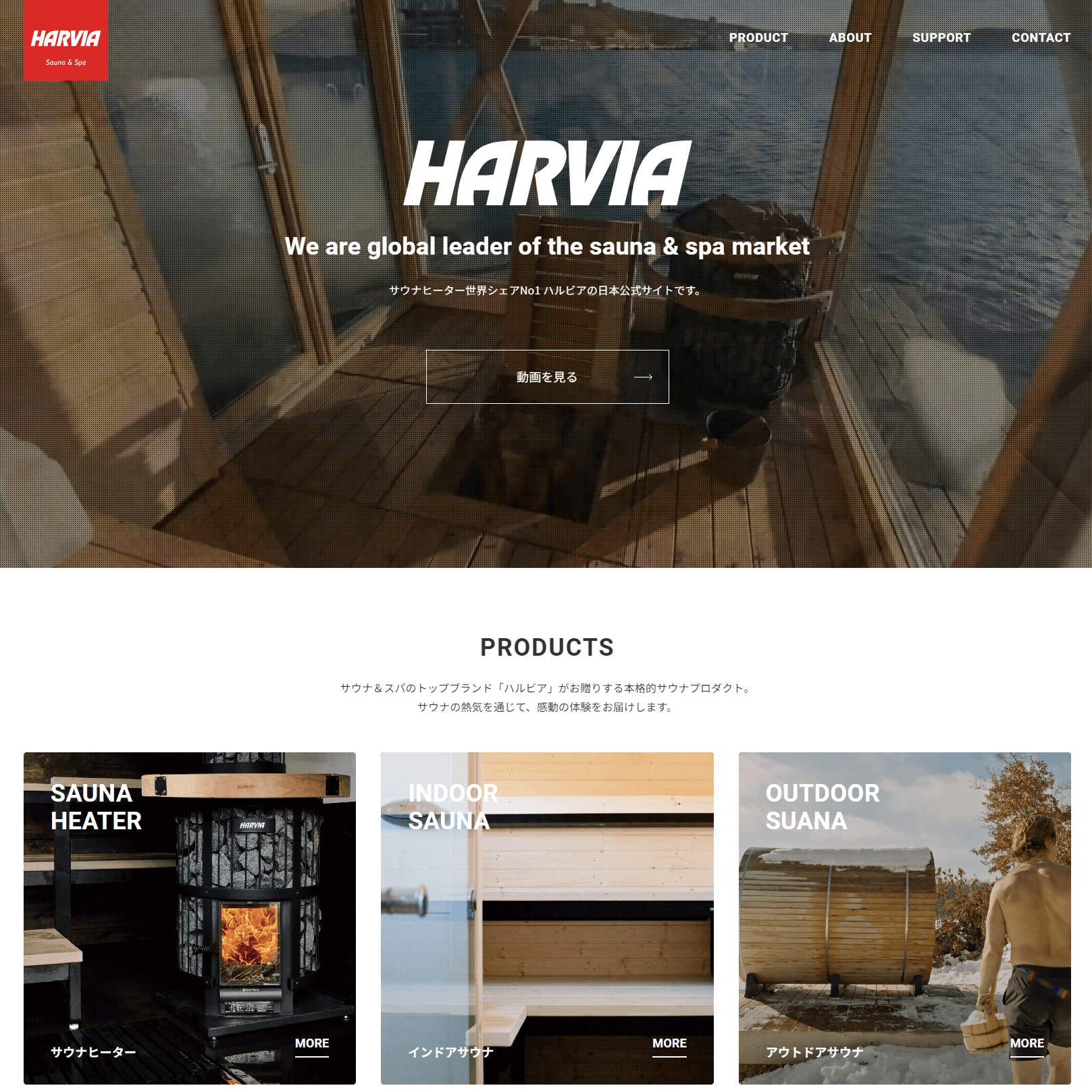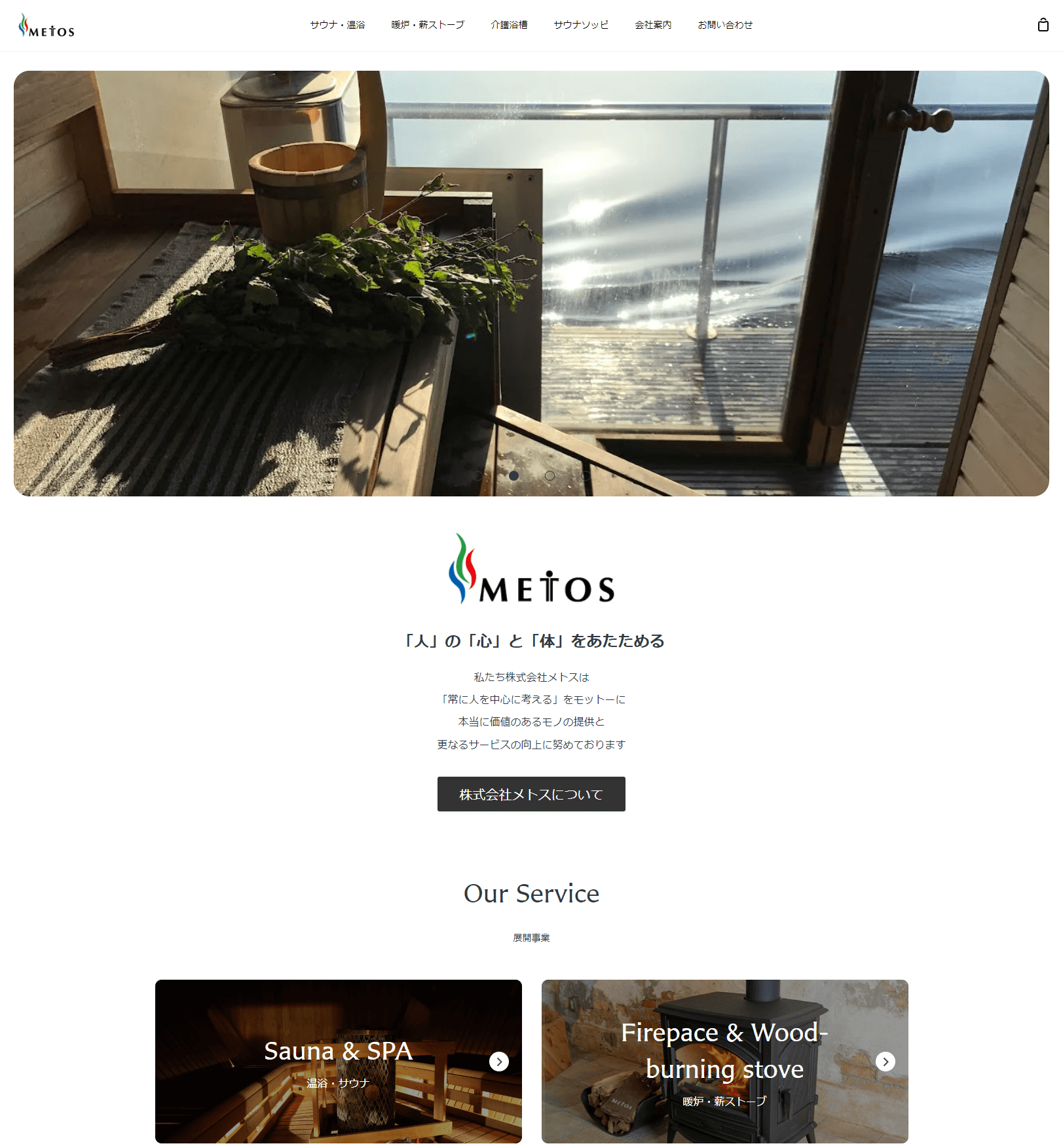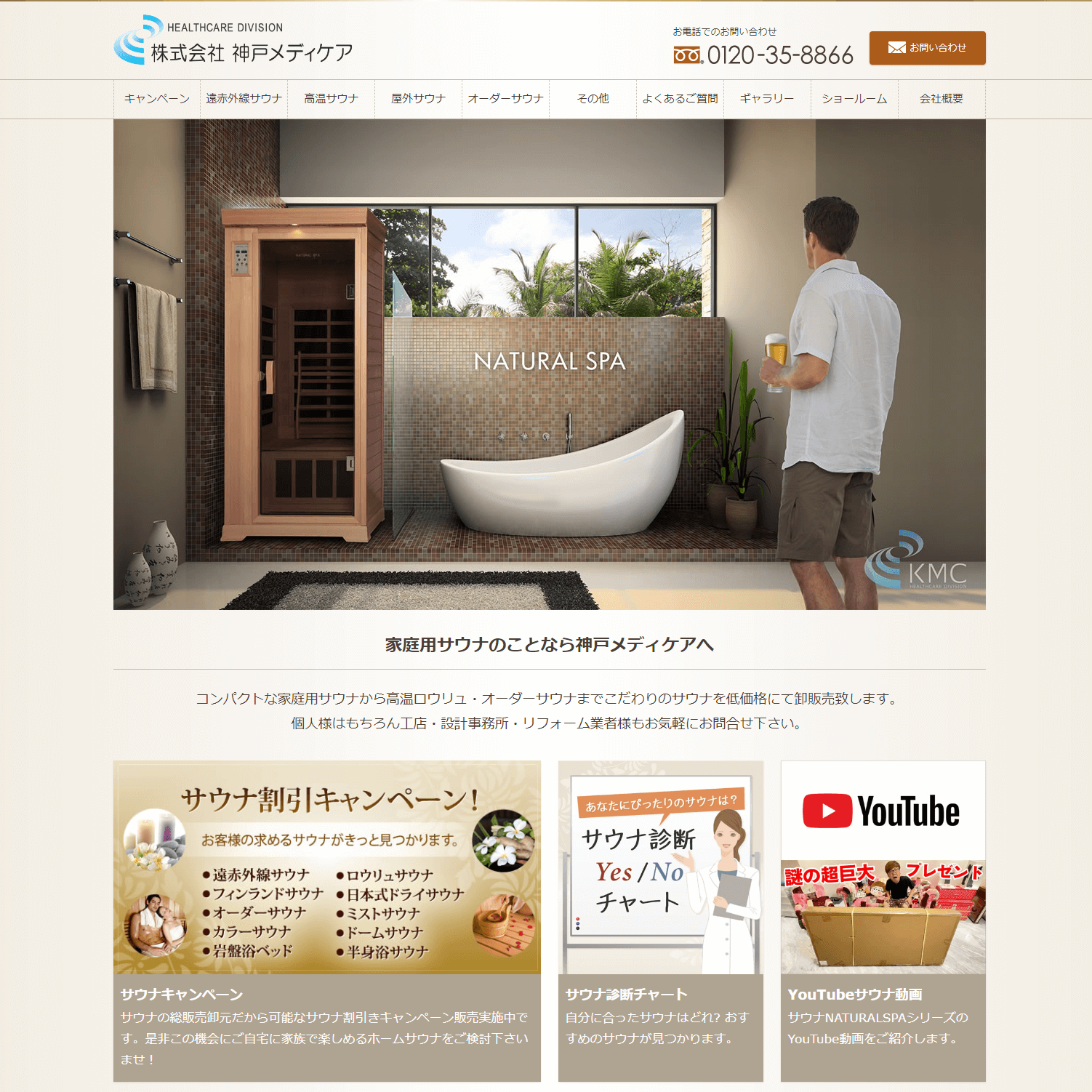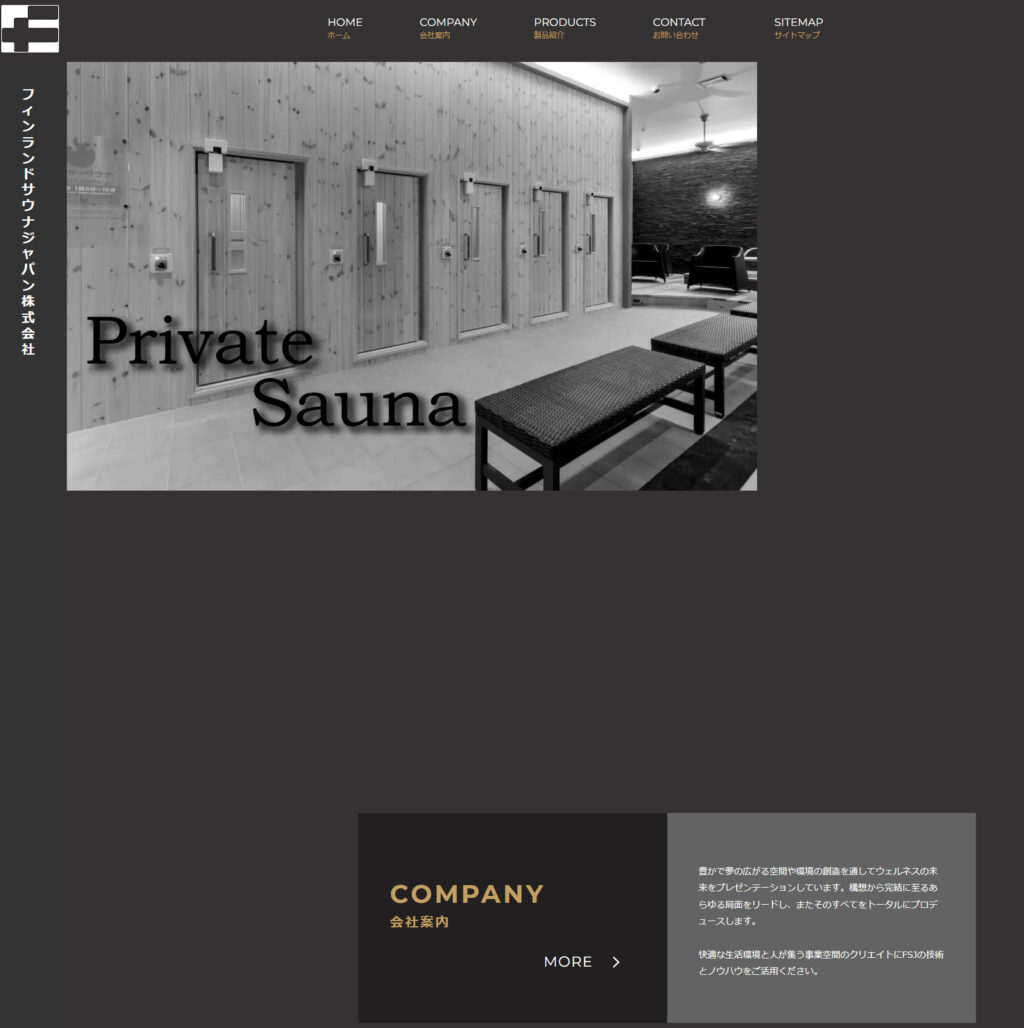サウナで整うというけれど、やり方が分からないとお考えではありませんか。サウナで整うためには正しい入り方を知らなくてはなりません。そこで本記事ではそんなお考えを払拭すべく、サウナで整う基本的な入り方を紹介します。この記事を最後までお読みいただければ、あなたも、整え方をマスターしたサウナーになれることでしょう。
サウナの起源
サウナは、フィンランドを起源とする伝統的な健康法であり、社交の場としても利用され、古代からさかのぼる歴史があります。ここでは、サウナの起源についてや日本のサウナについて解説します。
サウナの発祥はフィンランド
サウナの起源は古代フィンランドにさかのぼり、約2,000年の歴史があります。最初のサウナは、地下に穴を掘ったり、石を積んだりして作られていました。フィンランドの先住民が、寒冷な気候の中で体を温めるためにサウナは作られました。
その後サウナはフィンランドだけでなく、近隣のロシアやスウェーデン、バルト三国、スカンジナビア地域などに広がりました。
日本のサウナ
日本におけるサウナの始まりは、1952年に開催されたフィンランドのヘルシンキオリンピックの際、フィンランドの選手がサウナを持ち込んでいるのを見てからといわれています。一方、日本には古代から「蒸し風呂」や「岩風呂」の入浴文化がありました。
そのため、日本のサウナは、伝統的な入浴文化と、西洋のサウナ文化が融合し、独自のスタイルとして発展してきました。
サウナの「ととのう」とは?
昨今では、テレビやインターネットなどのさまざまな媒体で「ととのう」という言葉を耳にするようになりました。ではそもそも「ととのう」とはどういう状態でしょうか。ここでは、サウナの「ととのう」について解説します。
サウナでととのうとは
サウナで「ととのう」とは、サウナで体が温まった状態から、水風呂で一気に体を冷やすことで、頭がスッキリした感覚を得られることをいいます。体を温めることで体中の血流がよくなり、血流に乗って多くの酸素が脳に行き渡り、リラックスした状態になります。
その状態で水風呂に入ることにより、体は一気に冷やされ落ち着きますが、頭だけに興奮状態が残り、高揚した気分になります。これが「ととのう」です。
ととのうためのポイントや注意点とは
サウナで気持ちよく「ととのう」にはどうしたらよいのでしょうか。サウナを気持ちよく利用するためには、事前に知っておきたいポイントがあります。ここでは、ととのうためのポイントや注意点について解説します。
水分補給は必須
サウナは高温多湿の環境で行われる健康法であり、体に多くの利点がある一方で、適切な水分補給が非常に重要です。サウナでは大量の汗をかくため、入る前・休憩中・出た後それぞれのタイミングで、十分に水分補給するようにしましょう。
また電解質の補給も意識したいところです。サウナでの発汗により、体内の電解質も失われます。とくに長時間のサウナを行う場合は、適切な電解質(ナトリウム、カリウム、マグネシウムなど)を含むスポーツドリンクを選ぶことで、脱水症状の予防に最適です。
「サウナ→水風呂→休憩」を繰り返す
サウナでととのうためには「サウナ5分・水風呂1分・休憩10分」で1セットとし、2~3セットをおこなうのが効果的といわれています。
体調不良時には入らない
体調が悪い状態でサウナに入ってしまうと、脱水症状や立ちくらみの危険性がありますので、絶対に入らないようにしましょう。また、アルコールを摂取した状態でサウナに入るのは絶対にNGです。
マナー違反であるのはもちろん、サウナとアルコールの血管拡張効果が掛けあわされ、頭痛や熱中症のリスクが高まり危険です。
利用時のマナーを守る
サウナに入る際は、以下のマナーを守り、周囲に迷惑をかけないようにしましょう。
・入る前に体と頭を洗う
・大声で話さない
・タオルを敷いて直に座らない
・タオルで場所取りしない
・サウナ内でタオルを絞らない
・水風呂の前に汗を流す
以上のようなマナーを守り、皆がリラックスできる空間の維持に努めましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回はサウナでの整え方、初心者でもわかる基本的な入り方について解説しました。サウナの発祥はフィンランドで、約2,000年の歴史があります。日本では、伝統的な入浴文化と、西洋のサウナ文化が融合し、独自のスタイルとして発展してきました。
「ととのう」とは、サウナで体が温まった状態から、水風呂で一気に体を冷やすことで、頭がスッキリした感覚を得られることをいいます。体は冷やされ落ち着き、頭に興奮状態が残り、高揚した気分になれます。
また、サウナに入る際には、事前に十分な水分補給をし、体調不良時には入らないようにしましょう。さらに、しっかりマナーを守り、周囲を不快にさせない配慮も大切です。さっそくサウナに行って、ぜひ「ととのう」に挑戦してみてください。